
「フリーランスで確定申告は不安…税務調査が怖い…」そんな悩みをお持ちのあなたへ。
本記事では、フリーランスが知っておくべき税務調査に関する重要なポイントを解説しています。
税務調査の対象となる可能性、調査の種類、調査内容、発生するリスク、調査に備えるための対策など、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。
正しい知識を身につけ、税務調査に備えましょう。
フリーランスは税務調査の対象?可能性と対策
フリーランスは、会社員と比べて税務調査の対象になるケースが多いとされています。
これは、自分で確定申告を行う必要があるため、申告漏れや誤申告のリスクが高いためです。
さらに、会社員のように給与から税金が天引きされることがないため、自分で納税額を計算し、納付する必要があります。
そのため、税務調査では、申告内容の正確性や納税義務の履行状況が厳しくチェックされるのです。
税務調査では、申告内容に加え、収入や経費の根拠となる資料の提出を求められることもあります。
そのため、フリーランスは日頃から帳簿をきちんとつけ、領収書などの証拠書類を保管しておくことが重要です。
加えて、税務調査に備え、必要な知識を事前に身につけておくことも大切です。
税務調査は、申告内容に誤りがあった場合や、納税義務を履行していない場合に行われます。
税務調査では、税務署の職員が事業所や自宅を訪問し、帳簿や書類を調べます。調査の結果、申告漏れや誤申告が認められた場合、追徴税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があります。
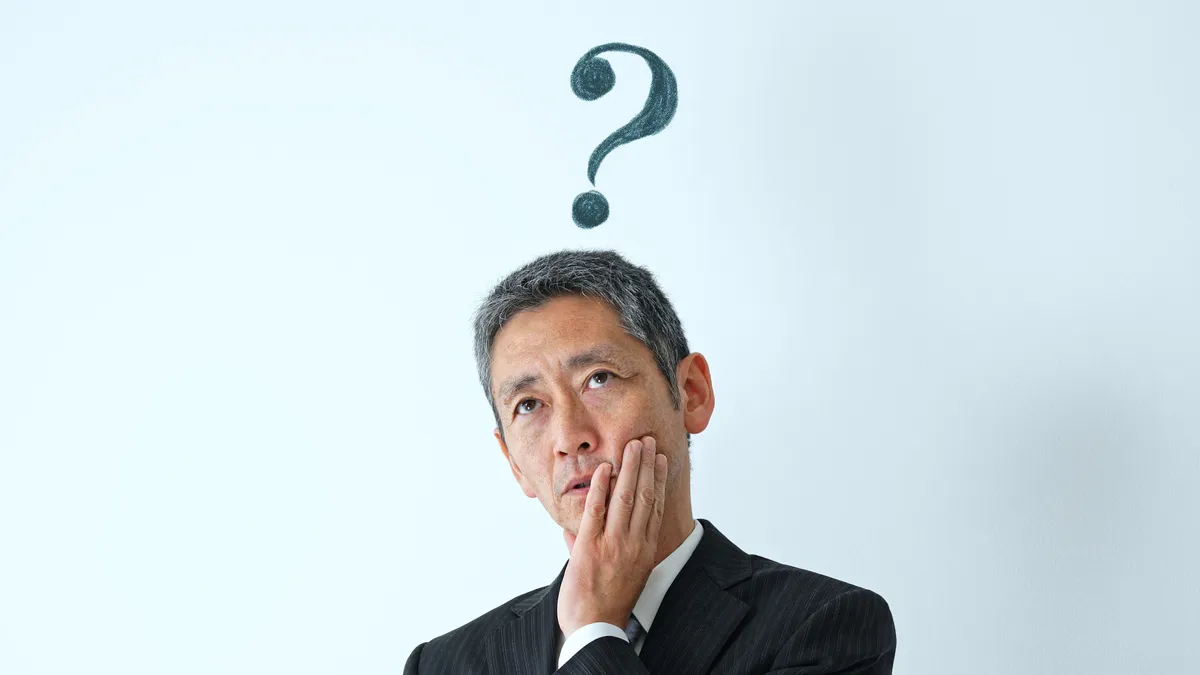
税務調査はフリーランスを含むすべての事業主が対象
税務調査は、納税者が提出した申告内容の正確性を検証するために実施されます。
対象となるのは、個人事業主や法人企業など、あらゆる事業者です。
フリーランスも事業者としての立場であるため、税務調査の対象となります。
申告漏れや脱税の可能性は、どの事業者にも存在するため、税務当局は、不審な事業者に対しては特に厳しい調査を実施することがあります。
強制捜査と任意調査:調査の種類と内容
税務調査は、強制調査と任意調査という2つの方法があります。
強制調査は、裁判所の令状によって行われる調査で、不正行為の疑いがある事業者の自宅や事務所を強制的に調査します。
この調査は、事業者側の同意は必要なく、拒否することはできません。
一方、任意調査は、事業者の同意を得て行われる調査です。
事前同意が必要なため、調査そのものを拒否することはできませんが、事前に都合の良い日時を調整したり、不測の事態が発生した場合には延期を依頼することも可能です。
申告内容の精査:調査の目的と内容
税務調査は、事業者が申告した内容の正確性を検証するために、税務当局が実施する重要な手続きです。
調査は、事業者の自宅や事務所への訪問によって行われ、帳簿や書類の精査、事業者への質問、在庫や現金などの確認など、多岐にわたる内容を網羅します。
調査では、申告内容の正確性を徹底的に確認するため、事業者にとって負担が大きくなる可能性もあります。
誤りがあれば追徴課税
税務調査では、過去の申告内容の誤りが発見されることがあります。
申告内容に誤りがあり、税金の額が訂正された場合、不足していた税金を納付する必要があります。
さらに、申告漏れに対するペナルティとして、罰金も課される場合があります。
この不足税金と罰金の支払いを追徴課税といい、申告漏れ金額が大きい場合は、罰金の負担が非常に大きくなるケースも少なくありません。
不正行為は罰則の対象
税務調査で不正が見つかった場合、様々な罰則が適用される可能性があります。
その中には、追徴課税と呼ばれる税金に加えて、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税といった加算税が課せられるケースがあります。
さらに、納税期限までに税金を支払わなかった場合、延滞税が課されることもあります。
不正の内容によっては、刑事罰として懲役刑が科せられる場合もあるため、脱税は非常に重い罪と認識しておく必要があります。
具体的には、申告漏れや虚偽申告といった不正行為は、税務上の重大な違反とみなされます。
税務当局による調査で不正が判明した場合、申告漏れ部分に対する税金に加え、加算税や延滞税が課されます。
加算税は、申告漏れや不納付の状況に応じて異なる税率が適用され、不正行為の重大性に応じてその額が大きくなります。
特に重加算税は、悪質な脱税行為に対して課されるもので、通常の加算税よりも高い税率が適用される場合もあります。
また、不正行為が刑事罰の対象となる場合もあり、その場合は懲役刑が科せられることもあります。

フリーランスが受ける税務調査の流れと手順
フリーランスが税務調査を受けるときは、税務署からの調査通知を受け、その後調査官との面談、帳簿・資料の提出、質問への回答、調査結果の通知、追徴税額の納付といった流れで進みます。
下記ではその流れについて解説していきます。
事前通知:調査開始前に通知書の送付
税務調査の実施前に、税務当局から事前通知が行われるのが一般的です。
通常は、納税者に電話で口頭による事前通知が行われます。
ただし、近年では、事前通知に先立ち、調査通知が送付されるケースが増加しています。
調査通知は、事前通知の内容の一部を抜粋したもので、以前は、事前通知を受けてから実地調査までに修正申告を行えば、ペナルティは課せられませんでした。
しかし、この制度の悪用が問題視されたため、調査通知が導入されました。
調査通知後に修正申告した場合も、一定の罰金が課せられる可能性があるため、注意が必要です。
事前通知では、調査の開始日時や場所など具体的な内容が伝えられます。
そのため、スケジュール的に問題がある場合は、調査担当者へ日程調整の依頼を行うことをおすすめします。
実地調査:税務職員が事業所や自宅を訪問
税務職員による実地調査は、自宅や事業所への訪問によって行われます。
調査では、帳簿を中心に、様々な書類の内容が精査されます。
現金や在庫などの実物についても確認が行われ、申告内容との照合を通じて、誤りがないか確認されます。
さらに、納税者に対しては、申告内容に関する質問がなされることもあります。
調査結果の通知:調査結果は後日送付
税務調査は、数日にわたり実施され、最終的に調査結果が報告されます。
問題がなければ申告は承認され、調査は終了となります。
指摘事項がある場合は、税務署から連絡が入ります。
顧問税理士がいる場合は、税務署から税理士に連絡が入るケースが一般的です。
調査結果に異議がある場合は、税務署に対して反論することも可能です。
必要があれば修正申告:調査結果に基づいた対応
税務調査で申告内容に誤りが見つかった場合、修正申告が必要となります。
修正申告後には、追徴課税が発生し、過去に納付していなかった税金に加えて罰金も支払うことになります。
しかし、調査結果に納得がいかない場合は、修正申告を行わず、税務署からの更正通知を待つという選択肢もあります。
更正通知は、税務署が税額を決定したことを示すものです。
更正通知の内容に異議がある場合、または納税者が更正通知に応じない場合は、裁判で争うことになります。

税務調査の対象となりやすいフリーランスの特徴
フリーランスは、会社員と比べて税務申告に関する知識や経験が少ないため、誤った申告をしてしまう可能性があります。
そのため、税務調査の対象となりやすいケースがあります。
以下では特に対象となりやすいフリーランスの特徴をご紹介します。
急激な売上の変動
事業の売上は、税務調査の対象となる重要な要素の一つです。
税務署は、企業の過去から現在までの売上推移を綿密に分析し、著しい増減があれば、その理由を調査することがあります。
特に、急激な売上減少は、売上隠しの可能性を疑われやすいため、注意が必要です。
税務署は、同業種の企業と比較して、売上の増減が極端な場合にも、その理由について詳しく調べる傾向があります。
たとえば、特定の期間において、売上額が大幅に減少した場合、税務署は、その理由として、売上を隠蔽している可能性を疑うことがあります。
また、同業種の企業と比較して、売上額が著しく低い場合も、調査の対象となる可能性があります。
税務調査の対象となる可能性を減らすためには、売上を正確に記録し、必要に応じて、売上減少の原因を説明できるよう、適切な資料を保管しておくことが重要です。
また、税務申告の際には、売上に関する情報を正確に申告し、税務署の質問に誠実に対応することが大切です。
開業後数年経過
フリーランスは、開業から数年が経過すると税務調査を受ける可能性が高まります。
税務調査では、原則として過去3年間分の帳簿や書類を調査対象とするのが一般的です。
これは、税金の時効が5年であるため、税務署は時効が到来する前に調査を行い、脱税の疑いがあれば追徴課税を行うことを目的としているからです。
開業当初は、会計処理の知識が不足しているために、誤った方法で帳簿を付けているケースも少なくありません。
このような状況では、税務調査で指摘を受けてしまう可能性も高くなります。
そのため、フリーランスは税務調査に備え、正しい会計処理を心がけることが重要です。
正しい会計処理を行うためには、会計ソフトを利用したり、税理士に相談したりすることが有効です。
会計ソフトを利用すれば、自動で帳簿が作成されるため、ミスを減らすことができ、税理士に相談することで、専門的なアドバイスを受けることができます。
税務調査の実施率は意外と低い
日本の法人に対する税務調査の実施割合は3%です。
一方で、個人事業主に対する税務調査の実施割合は全体の1%程度とされています。
このことから、フリーランスが税務調査を受ける可能性は法人と比べて低いといえます。
しかし、フリーランスであっても、常に税務調査に備えることが重要です。
特に、売上規模が大きいフリーランスは、申告漏れによる金額が大きくなるため、税務調査の対象となる可能性が高まります。
税務調査は、いつ実施されるかわかりません。
そのため、フリーランスは、万が一税務調査を受けた場合でも対応できるよう、事前に対策を検討しておくことが大切です。

フリーランスが税務調査に備えるための対策
フリーランスは個人事業主として事業を行うため、税務調査の対象となるケースがあります。
税務調査は、申告内容の確認や不正な申告の有無を調べる目的で行われます。
そのため、税務調査を受ける際には、事前に適切な対策を講じることで、スムーズな対応が可能になります。
書類整理と保管
ビジネスにおいて、経費精算の際には、請求書や領収書などの書類が不可欠です。
これらの書類は、経費の正当性を証明する重要な根拠となります。
請求書や領収書が提示できない場合、経費として認められないケースも発生する可能性があるため、注意が必要です。
特に過去の取引の証拠となる請求書や領収書は、適切に管理しておくことが重要です。
取引が発生するたびに、請求書や領収書を発行してもらい、きちんと保管する習慣をつけましょう。
また、書類整理を行う際には、紛失した書類がないか確認することも忘れずに行いましょう。
取引先によっては紛失した際に再発行してもらえるところもありますが、義務ではないため拒否される可能性もあります。
申告内容の見直し
税務調査は、事業者にとって大きな負担となる可能性を秘めています。
調査を受ける前に、申告内容に誤りがないか、十分な確認を行うことが重要です。
特に申告漏れは、多額の罰金が発生する可能性があり、事業の安定経営を脅かす深刻な事態に繋がりかねません。
過去の申告内容を精査し、売上や経費、消費税などの数値が正確に記載されているか、会計処理が適切に行われているかを徹底的に見直しましょう。
自社の力量だけでは見落とす可能性もあるため、専門知識を持つ税理士に相談し、第三者の視点からチェックしてもらうことをおすすめします。
書類紛失時の対応
書類紛失時は取引先に再発行を依頼するようにしましょう。
ただし、再発行は取引先の義務ではないため、依頼が受け入れられない可能性も念頭に置いておくべきです。
請求書などがない場合でも、取引内容を確認できる他の書類があれば、経費として認められるケースがあります。
クレジットカードの明細書やメール、発注書などが代用として有効な場合があります。
書類を紛失した場合は、代用となる書類がないか、しっかりと確認するようにしましょう。
専門家への相談
税務調査は、企業にとって大きな負担となる可能性を秘めています。
複雑な税法を理解し、適切な対応を行うには専門的な知識と経験が不可欠です。
そのため、税務調査対策は、専門家のサポートを受けることが非常に重要です。
税理士は、税務に関する豊富な知識と経験を持ち、企業の税務調査対策を総合的にサポートします。
税務調査の進め方や必要な書類作成、調査官との対応など、あらゆる場面において適切なアドバイスを提供し、企業の負担を軽減します。
さらに、税務調査の際には、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
税理士が企業に代わって調査官とのやり取りを行い、適切な対応をサポートすることで、企業は調査に集中することができます。
税務調査の不安を軽減し、スムーズな調査進行を支援することで、企業の業務効率向上に貢献します。

まとめ
本記事では税務調査がどのように行われるのか、そしてフリーランスが税務調査を受ける際に気を付けるポイントなど解説いたしました。
これからフリーランスになる方や、現在フリーランスとして活躍されている方は、この記事でご紹介した内容を参考に税務調査に備えるようにしてください。
特に開業したばかりで会計知識に不安などがある場合は専門家のサポートを受けるようにしましょう。
あいせ税理士法人では、確定申告や設立開業、税務調査のサポートなど法人個人問わず行なっておりますので、まずはご相談ください。
税務調査のサポートでは、税務署から通知が来たタイミングでのご依頼でもサポートさせて頂きます。
東京都新宿区、山梨県甲府市に事務所を構えておりますので、お気軽にご連絡ください。
関連記事
- 税務調査の基礎知識|調査の時期や当日の流れ・準備するものなど詳しく解説
- そもそも税務調査とは ? はじめての場合のチェック ポイントも解説
- 節税 vs 脱税: 2つの違いと罰則を分かりやすく解説
- 税理士に相談すべき?よくある不安と解決策を徹底解説
- 税理士選びは地元が正解?メリットと注意点、選び方のポイントを解説
その他の記事
-

税理士会とは?何をしていてどんな特徴があるのか?
税理士会の基本概念と役割 税理士会とは、税理士法に基づいて設立された特別な法人組織で、全国の税理士を統括し、その活動を支援・監督する役割を持っています。 税理士が税理士業務を行う […]
2025/5/9 -

新宿周辺で評判の良いおすすめの税理士事務所をご紹介
経営者にとって、信頼できる税理士との出会いは事業の成功に大きく影響します。 特に新宿エリアは東京の中心ビジネス街であり、多くの優れた税理士事務所が集中しています。 本記事では、新宿周辺で評判の […]
2025/4/25 -

不動産に強い税理士の探し方|見るべきポイントとは?
不動産投資で税理士が必要な理由 不動産取引や投資には多額の資金が動くため、適切な税務処理が利益を大きく左右します。 不動産にかかわる税金は複雑で種類も多く、専門知識がなければ適切 […]
2025/4/21









.webp)
.webp)
.webp)