
「減価償却の計算って難しそう…」「定額法と定率法の違いがよくわからない…」そんな悩みをお持ちのあなたへ。
本記事では、減価償却の計算方法をわかりやすく解説します。
固定資産の減価償却とは何か、耐用年数の考え方、減価償却を行う目的やメリット、そして定額法・定率法などの計算方法について詳しく解説します。
さらに、減価償却できる資産とできない資産、減価償却を行う際の注意点なども詳しく解説しているので、会計処理の基礎知識をしっかり理解したい方必見です。
減価償却とは?
減価償却は、企業が事業で使用する固定資産の取得価額を、その資産の耐用年数に基づいて分割し、経費として計上する会計処理方法です。
固定資産は、通常営業サイクル以外で発生し、現金化または費用化に1年以上かかる資産を指します。
土地、建物、機械設備などが代表的な固定資産です。
中でも、時間の経過とともに価値が減少していく資産を、減価償却資産(償却資産)といいます。
一般的に、事業のために購入した物品は、購入時に費用として計上されます。
しかし、減価償却資産の場合、購入した年に全額を費用として計上することはできません。
一定額以上の減価償却資産は、購入費をすべて当年度の費用として計上せず、原則としてその資産の耐用年数に応じて分割して計上する減価償却を行います。
減価償却は、資産を使用する過程で減耗や機能低下が発生し、徐々に価値が減少していくことを前提とした会計処理です。
耐用年数が経過すると、当初の購入価額に見合う価値をほぼすべて使い果たすという考え方です。
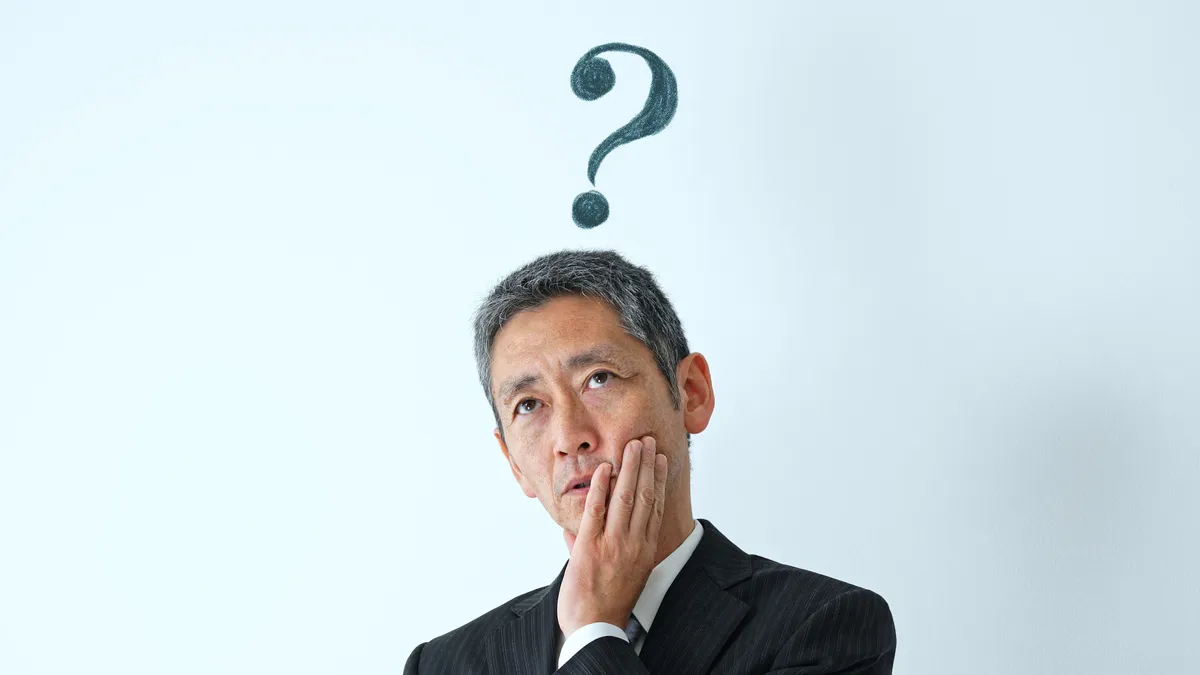
耐用年数の考え方と確認方法
減価償却を行うには、資産ごとの耐用年数を把握することが不可欠です。
会計と税法では、この耐用年数の考え方において差異が存在します。
会計上の耐用年数は、資産の使用方法や使用頻度などを考慮し、各企業が個別的に設定することが可能です。
例えば、同一の設備であっても、頻繁に使用する企業では3年、あまり使用しない企業では6年といったように、それぞれの状況に合わせて設定することができます。
これは、企業の実態に合致していれば、会計上の問題はありません。
しかし、税金の計算において、企業ごとに異なる耐用年数を設定してしまうと、課税の公平性が損なわれてしまいます。
そのため、税法上では、減価償却資産の種類、構造、用途などに応じて、一律の耐用年数が定められています。
この税法上定められた耐用年数を、法定耐用年数と呼びます。
資産の種類や細目ごとの法定耐用年数は、総務省の「償却資産の耐用年数」に規定されているほか、国税庁が定めた「主な減価償却資産の耐用年数表」でも確認することができます。
会計と税務で減価償却資産の耐用年数が異なる場合、処理が複雑になるため、実際には会計上も税法上の法定耐用年数に準じて減価償却を行うことが一般的です。
減価償却を行う目的とメリット
固定資産は長期間にわたって使用される資産であり、取得した年だけでなく、その後も継続して収益に影響を与え続けます。
そのため、取得した年に費用を一括計上してしまうと、その資産が複数年にわたって実際に収益に与えた影響が会計に反映されず、経営状況を適切に把握することができません。
そこで、年月の経過とともに価値が減少する固定資産の取得価額を使用可能期間内に配分し、収益と正しく対応させていく必要があるのです。
このプロセスのことを減価償却といいます。
減価償却は、会計上の処理だけでなく、課税の公平性を確保するためにも重要です。
減価償却の仕組みがなければ、利益が大きくなった年に固定資産を取得して費用を一括計上し、税負担を軽くすることが可能になってしまいます。
そのような事態を避けるため、法人税や所得税を計算する際に各事業年度に費用計上できる減価償却費は、「減価償却資産の取得価額を法定耐用年数で割った金額(償却限度額)まで」と決められています。
これにより、各事業年度における収益と費用のバランスを適切に反映し、税負担の公平性を確保することが可能になります。
減価償却を行わないと経営状態が正しく把握できない理由
減価償却は、企業の財務状況を正確に把握するために不可欠な処理です。
任意の処理ではありますが、節税対策や適正な会計処理という観点から、減価償却を実施することが推奨されます。
減価償却の取扱いは、個人事業主と法人では差異があります。
個人事業主の場合、減価償却は原則として義務付けられています。
そのため、減価償却の対象となる資産を取得した際は、所得税の確定申告において、法定耐用年数に基づいた減価償却を適用しなければなりません。
法人においては、0円から償却限度額までの範囲で任意の金額を減価償却費として計上することができます。
これを任意償却と呼びます。税法上、減価償却を実施しなくても問題はありません。
ただし、減価償却を実施しないということは、減価償却資産の取得価額を一度に費用として計上することができないことを意味します。
さらに、減価償却を省略したとしても、翌年度に2年分の減価償却費を計上することはできません。
つまり、法人が減価償却を実施しない場合、計上可能な損金が減少し、結果的に税負担が増加することになります。
減価償却できる資産は?

事業活動を行うために使用する資産には、一定期間の使用によって価値が減っていく「減価償却資産」と、時間の経過によっても価値が減少しにくい「減価償却対象外資産」の二つがあります。
減価償却できる資産の例
減価償却資産とは、建物、機械、車両など、企業の事業活動に不可欠な有形固定資産を指します。
これらの資産は、長期間にわたって使用することで、摩耗や老朽化によって価値が減っていきます。
そのため、企業は減価償却資産の価値の減少を会計処理上で反映するために、減価償却を行っています。
税法上は、取得価額が10万円以上で、使用可能期間が1年以上となる資産に対して減価償却が義務付けられています。
この取得価額には、資産の本体価格に加えて、設置費用、運送費用、購入手数料など、取得に伴う費用も含まれます。
取得価額が10万円未満の資産については、取得した事業年度に費用を一括計上することが可能です。
中小企業や個人事業主が青色申告を行う場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計額300万円を上限として費用を一括で経費に計上できる制度があります。
これは、少額減価償却資産の特例と呼ばれます。
減価償却できない資産の例
減価償却対象外資産には、土地、金銭、無形固定資産の一部が含まれます。
土地は、一般的に時間の経過とともに価値が減っていくことはほとんどありません。
減価償却は、一定期間の使用や時間の経過によって価値が減少していく固定資産に対して行われる会計処理なので、将来的な価値がゼロになることが見込まれる資産に適用されます。
一方で、土地や歴史的価値または希少価値のある資産、取得価額が1点100万円を超える美術品などは、時間の経過や使用によっても価値が減少しないと考えられるため、減価償却の対象外となります。
同様に、無形固定資産のうち借地権も、時間の経過によって価値が減少することは想定されないため、減価償却の対象から除外されます。
減価償却の方法:定額法・定率法の違い

減価償却は、企業が購入した資産の価値が時間とともに減少していくことを会計処理上で反映するために用いられる方法です。
主な減価償却方法には、「定額法」と「定率法」の二つがあります。
定額法は、資産の取得価額から残存価額を差し引いた金額を、耐用年数で均等に分割し、毎年同じ金額を償却する方法です。
これは、償却期間を通じて毎年一定の費用を計上したい場合に適しています。
定率法は、毎年一定の割合で償却する方法です。
この方法は、初期の期間に大きな償却費用を計上し、時間の経過とともに償却費用が減少していく特徴があります。
これは、資産の価値が初期に大きく減少し、その後は徐々に減少していくような場合に適しています。
その他、対象となる資産の種類によって、「生産高比例法」「リース期間定額法」などの方法も用いられます。
生産高比例法は、生産量に応じて償却を行う方法であり、リース期間定額法は、リース期間に応じて償却を行う方法です。
ここでは定額法と定率法の計算方法をご紹介します。
定額法:毎年一定額を償却する方法
取得価額100万円、耐用年数5年の減価償却資産を例に、定額法による減価償却費の算出方法について解説します。
定額法では、毎年同一額の減価償却費を計上します。
- 計算式
減価償却費(償却限度額) = 取得価額 × 定額法の償却率
償却率は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に基づいて定められています。
この例では、償却率は20%となります。
- 計算例
1,000,000円 × 20% = 200,000円
定額法では、最終年に固定資産が1円残るように、減価償却費を調整します。
そのため、最終年の減価償却費は、他の年よりも1円少なくなります。
この例の場合、取得年から4年目までは毎年20万円の減価償却費を計上し、最終年の5年目は19万9,999円を計上します。
定率法:毎年残存価値に対して一定割合を償却する方法
減価償却費を毎年一定割合で計上する方法を定率法といいます。
定率法では、減価償却費は取得価額から前年までの減価償却累計額を差し引いた金額に、定率法の償却率を乗じて計算します。
償却率は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められています。
未償却残高とは、減価償却資産の取得価額から、前年までに減価償却した累計額を差し引いた残高のことです。
未償却残高は年々減少するため、計上できる減価償却費も初年度が最も大きく、その後は償却が進むにつれて減少していきます。
償却が進んで、償却額が償却保証額を下回った場合は、計算方法が変わります。
償却保証額は、減価償却資産の取得価額に、省令で定められた保証率を掛けて求めます。
償却額が償却保証額を下回った場合は、期首の未償却残高に改定償却率を乗じて減価償却費を計算します。
改定償却率も省令で定められています。
例えば、取得価額100万円、耐用年数5年の資産を2012年4月1日以降に取得した場合の減価償却費を、定率法で計算してみましょう。
この場合、定率法の償却率は40%、改定償却率は50%、保証率は10.8%となります。
- 償却保証額:1,000,000×10.8%=108,000円
- 初年度の減価償却費:1,000,000×40%=400,000円
- 2年目の減価償却費:(1,000,000ー400,000)×40%=240,000円
- 3年目の減価償却費:(1,000,000ー400,000ー240,000)×40%=144,000円
4年目は、期首の未償却残高が100万円ー40万円ー24万円ー14万4,000円=21万6,000円となります。
これに償却率の40%を掛けると8万6,400円となり、償却補償額を下回るため、以降は計算方法が変わります。
- 4年目の減価償却費:(1,000,000ー400,000ー240,000ー144,000)×50%=108,000円
- 5年目も同額となりますが、定額法と同様に1円を残すため、実際の償却費は1円少なくなります。
- 5年目の減価償却費:108,000ー1=107,999円
定額法と定率法どちらで計算すべき?

定額法と定率法、どちらも最終的な償却額は同じですが計算方法によって減価償却費の計上額が異なり、税金への影響も異なります。
定率法は、固定資産の取得価額に対して一定の割合で減価償却費を計算する方法で、取得した年に多くの減価償却費を計上できるため、購入直後の税負担を軽減できます。
一方、定額法は、取得価額を耐用年数で割った金額を毎年一定額として減価償却費を計算する方法で、毎年同じ金額の減価償却費を計上するため、費用の計算が容易で、資金計画を立てやすくなります。
早期に節税効果を得たい場合は定率法が有利ですが、定額法はゆっくりと償却するため、高税率が課税される所得部分を減らすことができ、トータルの節税額が大きくなる傾向があります。
例えば、課税所得1,000万円の個人事業主が600万円の車を6年間で償却する場合、定率法では最初の数年は高額な減価償却費を計上できますが、定額法では毎年100万円ずつ減価償却費を計上することで、高税率が課税される所得部分を減らし、トータルの税金を抑えることができます。
なお、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアの計算方法は定額法と決められています。
また、法人はそれ以外の資産については定率法、個人事業主はすべての減価償却費を定額法で計算するのが原則となります。
ただし、これらの資産以外については、税務署に届出をすることで償却方法を変更することも可能です。
定額法と定率法それぞれのメリットを比較検討し、事業の状況に合わせて適切な償却方法を選択することが重要です。
減価償却を行う際の注意点
減価償却を正しく行うためには、計算方法だけでなく、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
特に、資産の売却や取得のタイミングによって、減価償却の計算方法が変化する場合があるため、注意が必要です。
ここでは、減価償却を行う際に留意すべき3つのポイントについて解説します。
減価償却途中の資産を手放す場合の会計処理
減価償却中の資産を売却する場合、処分時点で適切な会計処理を行う必要があります。
資産の処分方法は、廃棄、除却、売却の3つに分類されます。
廃棄とは、資産の価値が失われ、もはや使用不可能になった状態を指します。
この場合、資産の帳簿価額は損失として計上されます。
除却は、資産が破損したり、陳腐化したりして、修理や改造が経済的に合理的ではないと判断された場合に行われます。
この場合、資産の帳簿価額は損失として計上されます。
売却は、資産を第三者に譲渡する場合の処理です。
売却代金と資産の帳簿価額の差額が損益として計上されます。
売却による損益は、売却代金が帳簿価額を上回れば利益、下回れば損失となります。
事業年度の途中で資産を購入した場合の会計処理
事業年度の途中で取得した減価償却資産の減価償却費は、原則として月割計算で計算します。
ただし、重要なのは、資産を購入した月ではなく、事業で実際に使い始めた月からの計算になるということです。
例えば、12月決算の企業が5月に減価償却資産を取得し、6月から使用を開始した場合、初年度に計上できる減価償却費は、6月から12月までの7か月分となります。
一方、減価償却方法の一つである生産高比例法は、年の途中からの使用であっても月割計算は行いません。
耐用年数には規定がある
固定資産の減価償却を行う際は、その資産の耐用年数を正しく設定することが重要です。
耐用年数は、資産の種類や用途によって異なり、国税庁が定めた「耐用年数表」で確認することができます。
しかし、すべての固定資産が表に網羅されているわけではなく、適切な耐用年数を判断できない場合もあります。
耐用年数を誤って設定すると、税金計算に影響が出る可能性があります。
そのため、耐用年数の決め方に迷った場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
税務署でも相談を受け付けていますので、必要があれば相談してみましょう。
あいせ税理士法人では、税務顧問や確定申告のサポートをはじめ、設立開業やBPO、助成金・補助金など、税務に関するあらゆるサポートをさせていただいております。
法人・個人問わず税金に関しては悩みがあると思います。
些細なことでも構いませんので、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
東京都新宿区と山梨県甲府市に事務所を構えております。
関連記事
- 節税 vs 脱税: 2つの違いと罰則を分かりやすく解説
- 税金対策はプロに相談!セカンドオピニオンが賢明な選択
- 補助金・助成金も税金がかかる?会計処理の注意点
- 法人税の予定納税とは?概要と基本知識について解説
- 事業計画書の作成を税理士に依頼するメリットと注意点
その他の記事
-

税理士会とは?何をしていてどんな特徴があるのか?
税理士会の基本概念と役割 税理士会とは、税理士法に基づいて設立された特別な法人組織で、全国の税理士を統括し、その活動を支援・監督する役割を持っています。 税理士が税理士業務を行う […]
2025/5/9 -

新宿周辺で評判の良いおすすめの税理士事務所をご紹介
経営者にとって、信頼できる税理士との出会いは事業の成功に大きく影響します。 特に新宿エリアは東京の中心ビジネス街であり、多くの優れた税理士事務所が集中しています。 本記事では、新宿周辺で評判の […]
2025/4/25 -

不動産に強い税理士の探し方|見るべきポイントとは?
不動産投資で税理士が必要な理由 不動産取引や投資には多額の資金が動くため、適切な税務処理が利益を大きく左右します。 不動産にかかわる税金は複雑で種類も多く、専門知識がなければ適切 […]
2025/4/21









.webp)
.webp)
.webp)